
2020年8月、構造計画研究所とカサレアルは、Javaへのスキルエンハンス〜Spring Frameworkによる RESTful Webサービス入門トレーニングを行いました。
構造計画研究所では、配属先により扱う技術が多種多様なため、全社の新人研修を終えるとOJTを中心として、それぞれの職種に必要な専門知識を習得し業務の全体について学びます。わからないことがあってもすぐに調べることができ、コピペでモノを量産できる今、「人」を中心に、多様性を大切にしている構造計画研究所が最も重視したのは「基礎技術としてのプログラミングを体系的に習得すること」。プログラムをちゃんと書くとはどういうことか、プログラミング経験が異なる新入社員〜入社3年目までを対象に行ったカサレアルの研修についてお話を伺いました。
Javaへのスキルエンハンス研修 担当者


OJTの前に体系的に基礎知識を習得したい

早速ですが、カサレアルに最初にお声掛けいただいたときの課題感についてお聞かせください。構造計画研究所は、新入社員研修をOJT中心で実施していたんですよね。OJTは業務に入って実践的に学んでいける一方、プログラミングの基礎を体系的に学習する機会は自分で作らないといけないですよね。そこに課題があったとか。
はい、以前は全社の新人研修としてプログラミング教育があり、新人はOJT開始時にはベーシックな知識を持った状態でそれぞれの業務にあたっていました。その後、全社の新人研修でプログラミング教育をする代わりに、各配属先で必要な専門知識を、OJTを中心に習得させるようになり、教育担当者の実力によって教育にバラつきが出るようになりました。
個々人がプログラミング知識をいかに身につけることができたかということは、数年経たないうちに大きな差になって出てきます。最近はわからないことがあっても、ちょっと調べれば出てきますし、よくわかってなくても騙し騙しでなんとかできちゃいます。
この技術力のバラつきが課題の1つにありました。
 中井さん
中井さん
なるほど。高度なコードを書ける人、難易度が高いものを作れる人というのが限られてくるんですね。旧来のアーキテクチャのアプリケーションをモダナイズしたり、新規にモダンなアプリケーション開発を行ったりといったことをやろうとすると、影響が大きくなってきそうですね。
また、もう1つ課題がありました。開発部分を外部委託して、プロジェクトマネージャの仕事がメインになると、余計に知識が身につきにくいということです。プロジェクト管理の側面でも技術力は必要になりますので、プログラミングに対する正しい知識は持っていなければいけません。だからこそきちんと、ちゃんと、体系的に学ぶべきだという議論がありました。
 中井さん
中井さん中井さんがそんな課題を抱えている中、とあるカンファレンスで出会ったのがカサレアルの小林です。
懇親会の場だからできた本音トーク
中井さんと小林は、2019年3月に開催されていたDevRelCon Tokyoで出会いました。
※DevRelCon…Developer Relations(デベロッパーリレーションズ:外部の開発者とつながり、製品やサービスを知ってもらうマーケティング手法のひとつ)に関する国際的なカンファレンス。

小林と出会う前、社内で研修を変えようとしたり、他の研修機関を探したりといったことはあったのでしょうか?
構造計画研究所にはいろんな業種、いろんな部門があるので、社内の研修を変えるというのはちょっと難しいですね。全員が全員、同じ研修を必要としているわけではないので。
他の研修機関を探すのも、「やろう、やろう」と思っていても手が動きにくくて。
そんな中で、小林さんと仲良くなれたっていうのはよかったですね。あれはDevRelCon Tokyoの懇親会の場だったので、ぶっちゃけたハナシができました。それがなかったら、もしかしたら今も「やらないとね〜」って言いながら、研修やってなかったかもしれませんね。
 中井さん
中井さん
カンファレンスでは、中井さんがお持ちの課題について、小林とざっくばらんにお話しいただいたんですよね。それから実際にお問い合わせいただきましたが、「こういう技術を習得したい」「このカリキュラムは絶対に入れて欲しい」とか、どんなご要望をお持ちだったかお聞かせください。
どちらかというと、どのプログラミング言語にも通じる基礎的な部分を身につけさせたいと思っていました。業務でJavaは使わないものの、オブジェクト指向とかは知っておいて損はない部分がありますから。
また、世の中にはこういう動きがあるんだ、ということを知っておくのは重要だと思ったので、Spring Frameworkを入れてもらいました。枯れた技術を使い続けるのではなくて、世の中に新しい仕組みがあるなら取り入れられるようにしておきたいと。
 中井さん
中井さんカサレアルの提案
構造計画研究所からのご要望を汲み、カサレアルは ”Javaへのスキルエンハンス〜Spring Frameworkによる RESTful Webサービス入門トレーニング” を提案しました。まずは、Javaの基本文法を特に利用頻度の高いものを中心に、それからオブジェクト指向を活用したJavaプログラムの実装方法までを学習します。その後、Spring Frameworkを利用したWebアプリケーション開発を、RESTful Webサービスのアーキテクチャで学習します。
Javaの初学者、Java以外のオブジェクト思考プログラミング経験者が混在していましたが、座学の時間は最小限とし、ハンズオン、演習時間の比率を高くするとともに、研修終了後も独力で知識を身につけていってもらえるよう、ご自身で調べる力も養ってもらえるような内容にしました。
▼Javaへのスキルエンハンス〜Spring Frameworkによる RESTful Webサービス入門トレーニング
実施期間:2020年8月17日〜8月26日(計8日間)
1.Javaプログラミング入門(2日間)
Javaの文法を利用頻度の高いものを中心に学習。研修受講後の継続的な成⻑を視野に入れた構成に。
2.Javaプログラミング基礎(3日間)
実際の業務システムに対応できるよう、オブジェクト指向を活用した実装手法だけではなく、
クラスライブラリやデータベースアクセスの基礎など、開発現場で利用頻度の高い機能についても学習。
3.基礎からのSpringBootによるWebアプリケーション開発(3日間)
Spring初学者の方を対象として、基本的なWebアプリケーション開発方法を講義 + 演習で学習。

カサレアルの提案を見たとき、どのように思いましたか?
いただいたカリキュラムをIT教育に携わる責任者で議論して、「いいね!」と。Javaプログラミング入門、Javaプログラミング基礎、Spring Bootともちょうど良い内容でした。
 中井さん
中井さんカリキュラムはカサレアルの長年の経験に基づいたものになっているということも、研修内容がしっかりしているということもわかっていたので、これでお任せしました。
 濱田さん
濱田さんこうしてカサレアルの Javaへのスキルエンハンス〜Spring Frameworkによる RESTful Webサービス入門トレーニング が始まりました。新型コロナウイルスの感染拡大により、開催時期が後ろ倒しになる事態にもなりましたが、無事に8日間の研修を終えました。
新入社員〜入社3年目でさまざまな感想

実際にやってみて、受講者からどんな反応がありましたか?
今回は新入社員〜入社3年目まで含めた研修だったので、1年生からは「非常によかった」という意見が多く、プログラミング経験者のレベルによっては「物足りなかった」という意見もありました。
受講者のレベルもバラつきがある中で、講師がうまくコントロールして全体の成長を見ていただけたと思います。
 濱田さん
濱田さん「物足りなかった」という人も、ほとんど全員が「体系立てて、きちんと学んだことがなかったので、△△に関してすごく理解が深まった」と言っていました。
総じて、基礎をきちんと学ぶという研修にしてよかったと思います。
 中井さん
中井さん
新入社員の方々にとっては研修内容がまるごと学びになるし、入社年数が経っている方々へは更なる興味を起こせるし、一緒に受講する機会があったのはすごくよかったですよね。受講者のその後の様子はいかがですか?
今回は、いろんな部門をまたいで受講者を集めたので、横のつながりをこのまま維持していこうと話していましたね。
また、このときの受講者が最近、カサレアルの『JavaによるAndroidアプリ開発入門』を受講したのですが、それはここでJavaを学んだことからつながっています。
 濱田さん
濱田さん今後もデータ構造やアルゴリズム、「なぜ?」を学んでいきたい

今期はJavaではなく、GitとPythonの研修を行うことに決まりましたね。どんなことを期待されていますか?
今期も変わらず、プログラミングの言語を覚えるより、情報工学にもとづいてデータ構造やアルゴリズムを考えてちゃんと書くってことを学んで欲しいと思っています。このリクエストに対して今期はシンプルながらも汎用性が高いPython、バージョン管理システムのデファクトスタンダードともなっているGitの研修を提案していただきました。Javaから変わりましたが、お願いしたいところの真意はずれていないので、そこに当てはまるいろんなところをやっていただけると嬉しいです。
 濱田さん
濱田さん
他に、「こうしていきたい」といったことはありますか?
カサレアルの研修では、業務ではできない部分を補強できればと思います。業務では、もう既にあるものをカスタマイズしたり、ちょっと修正したり、穴埋めしているようなことも多くて、「本当にこの言語、自分で使いこなせているのだろうか?」という疑問が出てきます。
だから研修の中では、イチからきちんと自分で実装することができる感覚が身につけられればと思っています。なぜこれをやっているのか?というところを学習できればと。
 中井さん
中井さん
確かに、ゼロからちゃんと自分で作れると圧倒的な自信にもなりますし、応用力も身につきますもんね。
そうですね、コピペで量産できる時代なので、そういうことやっているとまずい、という問題意識を持てればいいですね。
 中井さん
中井さん※2021年度に実施したGitとPythonの研修について、受講者によるブログをぜひご覧ください。(2021/12/22追記)
多様性を大切にしつつも基礎をしっかり揃える
最後に中井さん、濱田さんに、研修実施の背景にある、構造計画研究所が大切にしていることについて話していただきました。
構造計画研究所には、国籍も含めて、多様な人たちが集まっています。コンピュータサイエンスを学んできた人だけじゃない中で、全員がきちんと基礎を学んでおくことの重要性、プログラミングとは、という部分をきちんと学べる研修の必要性を常に感じています。
たとえ担当するメインの業務が上流だろうと下流だろうと、技術知識のあるなしで、出てくるものの品質に差が出てきます。コンサルティングをやるにしても、最終的に作るもののイメージを持てているかどうかで提案のレベルも大きく変わってきます。より良い提案をするために、作るもののクオリティを上げるために、そして会話のレベルを合わせられるように、しっかりと基礎知識を学ぶことが重要なんです。
 中井さん
中井さんプログラミングの基本・基礎が我流にならないように、きちんとしたところで、きちんとした知識を入れる、というところに研修の目的があります。JavaでもPythonでも、オブジェクト指向を学べればいいと思っています。その後のOJTでは、プロジェクトの中で学んでいくことになるので、ある程度みんなが同じ状態で始められるようにできればと思います。
入社してくる新入社員は全員が全員、情報系というわけではなく、全員がプログラミングを経験しているわけではありません。その多様性が構造計画研究所のいいところです。だからこそ、基礎をしっかり揃えるのが重要だと実感しています。
 濱田さん
濱田さんカサレアル担当者からの声
講義中の質疑応答も活発にあり、集中して参加していることが伺えました。また、受講者間の雰囲気が良く、休憩中などにもお互いの認識の共有や質問などをしていました。ディスカッションを行うことで発展的な質問が出るなど、順調に学習が進んでいました。また、UnitテストのJUnitについての話では、興味を持たれている方も多かったです。
質問・ディスカッションも積極的に参加しており、良い復習と理解の定着ができたようです。オブジェクト指向については難しく感じているようでしたが、その利点は捉えられたようです。講義開始前にも休憩室で予習・復習などもしていたようです。
他の言語経験者の方はJavaとの違いに注目が行くようでした。ときおり他言語との違いも含めて話したので、Javaの特性がより理解できたようです。オブジェクト指向について深く学べたことを喜んでいた方もいました。
テンプレートエンジンなどに馴染みがない方が多く、Webアプリケーションの技術要素について苦戦されていたものの、現場で実践を重ねていけば活用できるようになるのではと思います。JavaScriptのフレームワーク(Angular、Vue.js)の話をしたときには、興味を持たれている方も多くいらっしゃいました。
顧客プロフィール
株式会社構造計画研究所
設立:1959年5月6日
資本金:1,010百万円
売上高:13,631百万円(2021年6月期)
営業利益:1,718百万円(2021年6月期)
従業員数:616名(2021年8月1日時点)


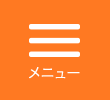

 1分で簡単!資料ダウンロードはこちら
1分で簡単!資料ダウンロードはこちら