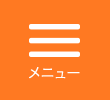コンテナ活用が進んでくると、次はマイクロサービスアーキテクチャに着目されますが、
マイクロサービス化においては様々な課題が発生することもあり、難易度が高いとされています。
これはDX推進におけるクラウドネイティブな取り組みを進める中で、多くの企業が直面する壁ですね。
この壁に向き合うための一つの考え方である「モジュラーモノリス」についての研修コース
『モジュラーモノリスから始めるマイクロサービス入門』を開発しましたので、
今回はそのコースのご紹介をさせていただきました。
モジュラーモノリスについては、24年11月に開催されたイベント「CloudNative Days Winter 2024」でも講演しておりますので、
ぜひこちらもご覧ください。
►講演動画『マイクロサービスアーキテクチャへのモチベーション整理とその複雑性に対する落としどころ』
モジュラーモノリスの研修コースカリキュラムは、2日間で構成されています。
マイクロサービスと関連するアーキテクチャを学び、
そこから目指すべき方向は何か(≒無理にマイクロサービスを選択しなくてもよいかもしれない)という点に着目し、
「将来的にマイクロサービスを目指すための第一歩を踏み出して行こう」
「まずはモジュラーモノリスの考え方に沿って準備をしよう」といった内容となっております。
今回のコース体験会では、本来のコースから要所をかいつまんでお話させていただきました。
体験会では、「マイクロサービスやミニサービスとしての分割の単位」「サービス間の依存関係」についてのご質問をいただきました。
(招待制の体験会につき、恐れ入りますが詳細は控えさせていただきます。)
マイクロサービスと聞くと、小さい機能単位でのサービス群であるイメージが強いですが、
まずはフロントエンドとバックエンドといった大きな括りでの考え方や、
ビジネスドメインの単位で大きく分けてから必要に応じて細分化する方法でよいかと考えます。
最初からマイクロサービスを作るのではなく、肥大化して扱いに困るようになったモノリスを
少しずつ分けていくことが成功への近道となるため、じっくり腰を据えて向き合っていく必要があるでしょう。
体験会を終えて
体験会は多くの方から高い評価をいただき、「モジュラーモノリスやマイクロサービスに関する知識を網羅的に得られた」「研修コースの全体像を把握できた」といった有難いコメントをいただきました。
一方「コードの中身を知りたかった」というご意見もございました。
本来の研修コースから、内容を圧縮してのご紹介だったためあまり触れることができませんでしたが、
『モジュラーモノリスから始めるマイクロサービス入門』は、
プログラム構成を作り替えたことによる副作用の有無や、リリース作業などの実運用面も見据え、
マイクロサービスを比較した際に従来とあまり変わらない点や、考慮しなければならない点についても詳しく触れています。
アーキテクチャや、プログラム構成に関する話題が中心となるため、初級者向けではなく中級者向けのコースであるという印象を持たれるかもしれませんが、
今後のプログラム構成において、コンテナ活用なども踏まえて皆様のお力になれればと考えております。
 併せてチェックしたい!カサレアルのマイクロサービス関連コース
併せてチェックしたい!カサレアルのマイクロサービス関連コース
・マイクロサービス概要
・マイクロサービスアーキテクチャにおけるトランザクション入門